怪談「受け取り」
ボクは宅配のバイトをしている。
あの、猫のマークで有名なところだ。
そのせいではないだろうけど、不可思議な体験をすることが多い。
この話は、その中のひとつ。
いつものように、ボクは配達する届け物を仕分けしていた。
普通免許は持ってるけど、バイトのボクは車を使えない。
だから、緑のボックスをのっけた手押しの台車が、ボク専用の配達車。
でも緑のボックスは、大きいようで、すぐにいっぱいになってしまう。
だから台車に積む前に、配達順番を考えて、仕分けをする必要があるんだ。
そうしないと効率よく配達できないし、荷崩れしてしまうこともある。
料理でいえば、仕込みみたいなものかな?
この作業は地味だけど、とても重要なんだ。
だから、ひとつひとつを手にとり、しっかりと住所を確認する。
そうして仕分けの作業をしていて、ボクは軽めの箱を手に取ると、
「おばあちゃんトコか」
と、何の気なしに呟いた。
“おばあちゃん”といっても、親戚とかそういうのじゃない。
単なる“お馴染みさん”。
このバイトをやってると、担当地域に“お馴染みさん”というのができてくるんだ。
よく行くお客さんや、印象の強いお客さん。
あまり行きたくないお客さんもいるけど…この届け先のおばあちゃんは逆。
おばあちゃんはいつも、届け物を受け取ると、配達票に自分の名前を書くんだ。
人柄を忍ばせる、丁寧で、綺麗な字。
大抵のお年寄りは判子を使うのに、このおばあちゃんは使わない。
ちょっと珍しい人。
そして届け物が完了すると、
「いつも、ありがとね」
と、おばあちゃんはニッコリ笑ってくれる。
「ありがとうございました」
と、ボクも頭を下げて応える。
何気ないことだけど、この仕事で一番うれしい時だね。
おばあちゃんは、人当たりがよくて、いつもニコニコと労をねぎらってくれるし。
暑い夏の日には、冷たい飲み物。寒い冬には、みかんをくれたりもする。
お線香の匂いがするところは、ボクに亡くなった祖母を思い出させ、懐かしく和ませてくれる。
だから配達に行くのは、いつも楽しみだったりするんだ。
配達票を見て、ポツと呟いたのも、そんな理由からだね。
台車を押して、おばあちゃんの家に着くと、ボクは低い柵を開けて小さな庭に入った。
いい忘れてたけど、印象に残ってるのは、もうひとつ理由があるんだ。
ここの家は、東京では珍しく、庭にお墓がある家なんだ。
っていっても、気味がわるいと思ったことは一度もない。
配達に行くのは、決まって昼間だからね。
夜中なら別かもしれないけど。
明るい昼日中じゃ、「へぇ〜」と思うくらいかな?
いまもそう。
特に気にすることなく、お墓の前を通って玄関にたどり着いた。
呼び出しベルはないので、茶色い木の柱を、コンコンと二回ノック。
返事を待ちながら、ボクはあたりを見回した。
小さな庭は、お墓のせいで、あまりスペースはない。
猫の額のような花壇に、真っ赤な彼岸花が咲いていた。
家の中から返事はなく、ボクはまた、コンコンと四回目になるノックをした。
それで、しばらく待っていたけど、返事はなかった。
いつもはこのくらいで、気づいてくれるんだけど…お留守なのかな?
そう思っていたら…
…ピュー……ピュー……
と。中から笛のような音が、かすかに聞こえた。
独り暮らしのお年寄りの家には、なんとも似つかわしくない音。
聞き間違いかな?
…ピュー……ピュー……
踵を返したボクに、また笛の音が呼びかけた。
あれ? いるのかな?
ボクは首を捻った。
お孫さんでも遊びに来てるのだろうか?
お孫さんが笛を吹いてて、それでノックが聞こえないのかな?
そんなことを思いながら、ボクはコンコンと六回目のノックをした。
「………はぁ…いぃ…」
今度は嗄れた、小さな返事が聞こえた。
「こんにちは〜。○○○運輸です〜」
ボクは、玄関越しに声をかけた。
するとさっきの笛の音にまじり、嗄れた声が聞こえる。
「…いま……でらんないの…ピュー…ごめんね……」
風邪でもひいたのかな?
ツラそうな声だ。
「そうですか。
お届け物なんですけど、どうしましょうか?
後でまたきましょうか?」
「…そこ…に……ピュー…置いといて…くれる…?」
「そこ…?」
「…お墓のトコ…ピュー……後で…取りに行く…から……」
そういうのは“玄関前配達”といって、厳禁なんだけど。
お客さんの要望なのだから、断るすべはない。
なにより病気のお年寄りを、無理に呼び出すのも気が引ける。
「わかりました〜」
ボクは了解の返事をすると、お墓のところに届け物を置いて、携帯電話の時計を見た。
こういうときは、配達票に日付と時間を書き記すんだ。
なにか問題が起きたり、配達センターで聞かれたりしたときの覚え書きみたいなものだね。
「…ごめんね……」
おばあちゃんの声が聞こえた途端、なぜか背筋がゾクゾクして身がこわばった。
いつものように、やさしい声なのに…。
「い、いえ。あ、ありがとうございました…ぁ…」
ボクは慌てて立ち上がると頭を下げ、なにかに急かされるように立ち去った。
次の日の朝。
ボクは目が覚めると、いつものようにTVをつけた。
バイトに出る前に、天気予報を見るのが日課になってるんだ。
しかし画面に映ったのは、美人のお天気お姉さんでも、天気図でもなかった。
それはなんとも、寝覚めのわるいニュース。
独り暮らしの老人が惨殺されたという、凄惨な事件だった。
「治安がわるくなったな…ホントに……」
そう呟くと同時に、ボクはギョッとした。
被害者は、あの、おばあちゃんだったのだ。
いっぺんに目が覚めきると、TV画面に釘付けになった。
どうやら事件は、昨日、玄関の土間の辺りで起こったらしい。
可哀相に…。喉笛を掻き切られて、そのまま放置されたとか……。
……喉笛を切られて…放置?
ボクは昨日のことを思い出していた。
あの苦しそうな声…
ピュー、という笛の音…
そ、それじゃ、ボクは、今にも死にそうなおばあちゃんと、あんな会話をしていたんだろうか……?
扉一枚の近さで、苦しんでいる人を助けずに、あんな能天気な会話を…。
知らなかったとはいえ、それはとても残酷で、なんともやりきれない…。
「よ、よかった…」
詳細を聞きながら、ボクは不謹慎ながらも、ホッと胸を撫で下ろした。
死亡推定時刻が、配達の時間と重なってなかったからだ。
その時刻は、ボクが伺った、二時間前……。
「う、うわぁぁぁぁぁぁぁっっっ!!」
悲鳴を上げるとボクは、布団を被ってガタガタと震えた。
誰だってそうなるだろ?!
だってニュースが正しければ、“ボクが伺った二時間前”に、おばあちゃんは亡くなっていたことになるんだ。
つまりボクは、すでに死んでいる人と、会話してたんだ……。
その日、ボクはバイトを遅刻した。
あんなことが起きて、ホントはバイトどころじゃないんだけど…。そうもいかない。
陰鬱な気をようやっと引きずり起すと、ノロノロとした足どりで、ボクは配送センターに現れた、
そしてボクを待っていたのは、センター長のものすごい叱責だった。
遅刻のことじゃない。
届け物がひとつ、行方不明になっていたんだ。
どうやら持ち出されたままで、配達完了にも、不在扱いで戻ってもいないのがあるらしい。
ボクはすぐにピンっときた。
おばあちゃんへの届け物だ。
昨日ボクは、慌ててあの場を立ち去った。
そのせいで配達票を抜き忘れ、配送センターでは行方不明ということになってしまったんだろう。
ボクは事情を説明すると、すぐにおばあちゃんの家へ向かった。
正直、ボクの足どりは、軽くはない。
昨日、ボクの背筋を凍らせた原因も、いまとなってはわかるから。
しばらく近寄りたくはなかったけど…届け物は、大事な預かり物。
それが行方不明では、会社の信用に関わるもの。
いくらバイトだからって、バイトにはバイトなりのプライドがある。
それに配達票を持ち帰るくらいなら…そう、コワイこともないだろう…。
おばあちゃんの家は、昨日きた時と、なんら変哲はなかった。
てっきり、黄色いテープとか巻かれてると思ったんだけど…。
現場検証とか、終わったせいなのかな?
一応、場を荒らさないように、ボクは注意深く柵を抜けると、お墓の前にきた。
でもそこには、届け物の姿はなかった。
そのかわり、小石をのせた配達票があった。
誰が届け物を持っていったんだろう…。
配達票を拾いあげて見ると、そこには名前が書いてあった。
人柄を忍ばせる、丁寧な字…。
まちがいなく、おばあちゃんの字で、こう書き添えてあった。
「ありがとね」
ボクは帽子を脱いで手を合わせると、お墓に深く頭を下げた。
「ありがとうございました」
< FIN >

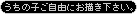


[ FrontPage ] - [ Next: 怪談「いぬ」 ]
※.この話はフィクションです。
実在する団体・個人に一切関係はありません。